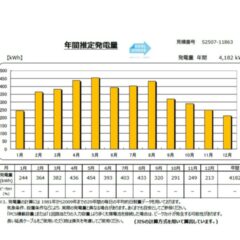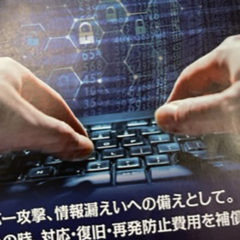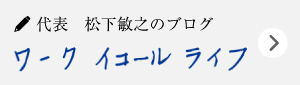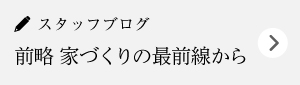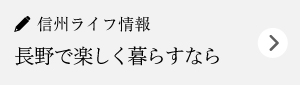水道料金高騰に備える「節水」アイテムのご紹介
道路の陥没事故を引き起こした下水道の破損がありました。老朽化した配管の補修費用をまかなうため、水道料金が大幅に値上げされるというニュースも耳にしました。家を建てるにあたって「節水」を意識したいと思いますが具体的にどんな取り組みが可能でしょう?
素晴らしい視点ですね。上下水道などのインフラが老朽化する中、その維持費を私たちが負担する流れは止められません。
これからの家づくりにおいて「節水」はますます重要なテーマになってきます。
今回は、導入しやすいものから少々の工夫やコストが必要になるものまで、住宅でできる「節水」の具体策をご紹介します。
「節水型トイレの導入」
最近のトイレは、1回の「大」の洗浄で4L〜5L、「小」の洗浄で3L以下が一般的です。10年以上前のトイレは1回で約13L使っていたため、水の使用量は半分以下に抑えることができます。コストも従来品とほとんど変わらず、多くの住宅で標準仕様として採用されています。
「節水型シャワーヘッド」
手軽に交換できる「節水アイテム」で空気を含ませることで水圧はそのままに、水の使用量を30〜50%もカットできます。
価格も5千円〜1万円程度と手頃で、既存の住宅でもすぐに導入できますし、新築の住まいではほとんど標準仕様となっていることが多いです。
「食洗機の活用」
意外に思われるかもしれませんが、食器を「手洗い」するよりも、水の使用量が1/6〜1/9まで大幅に削減することができます。
設計段階で「ビルトインタイプ」の物を採用することが理想的ですが、卓上用の物を後付けすることも可能です。
「雨水タンクの設置」屋根に降った雨水を家庭菜園など庭の水やり用に利用することが可能です。100L〜200L程度のタンクが数万円で購入でき、
たとえば長野市では設置費用の半額まで(額では2.5万円)まで助成金が出る制度もあります。
「浴槽の残り湯を洗濯に再利用しやすい設計にする」
多くの洗濯機には「風呂水利用」の機能があり、ホースも付属していますが、浴槽と洗濯機置き場を隣接して設計することで、
ホースの取り回しがラクになり、より快適に使えるようになります。1回の洗濯で最大100L近くも節水できる場合もあります。
「洗い」は残り湯、「すすぎ」は水道水と使い分けることで、衛生面も安心です。
さらに「オプション」にはなりますが、浴槽の残り湯を自動で洗濯機へ送水する専用の配管システムを
設計段階から組み込むことも可能です。ホースが不要となり、ボタンひとつで自動吸水され、より快適に使用することが可能です。
節水の工夫は、毎日の暮らしの中で無理なく続けられることが大切です。
住まいづくりの段階から意識しておくことで、将来的な水道料金の節約も可能です。